シゴトビトの言葉学
[第39講] 炎重工株式会社 取締役 萩野谷 征裕のコトバ
毎月1回開催の「しごとトークカフェ」。そこで社会人のゲストが語る、働き方、暮らし方、生き方とは?岩手で働く社会人たちからのメッセージを「シゴトビトの言葉学」として紹介します。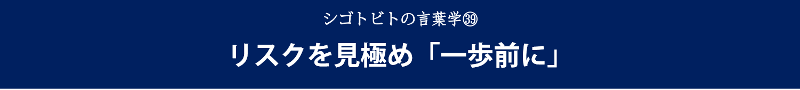
東京・足立区の出身で高校、大学は慶應。公認会計士を目指す友人から刺激を受け「やるなら難しいことに」と資格取得を目指した。難関を突破し、就職したのは日本の4大監査法人の一つ。有名企業が顧客でその監査や、これから上場をしようとする企業の助言・指導業務、IPO監査(上場準備監査)などをしていた。土曜日は、会社の有志らが集まり勉強会。ここで出会ったのが現在の炎重工社長、古澤洋将だった。古澤は、つくば市の医療・介護ロボットなどを製造販売する会社でロボット技術の研究開発をしていた。「食糧生産のデジタル化、工業化をするため起業したい」。「面白そう」とは思ったが、「今の仕事を捨てて未知のベンチャーに」という進路選択に悩んだ。考えたのは「取り返しのつかないリスクなら背負う必要はないが、なんとかなるなら一歩前に」
炎重工の目指すもの
炎重工の「炎(ほむら)」はNHKの大河ドラマ「炎立つ」から。盛岡市の作家高橋克彦の原作で、奥州藤原氏がみちのくに独自文化を花開かせた歴史の再現を目指すという意気込みを表している。目指すのは食糧生産の自動化だ。他企業があまり参入していない水産業をフィールドに水の上は「マリンドローン」で、水の中では特許を持つ「生体群制御®」の技術を使う。「湾内で育てた小さい魚→湾外の外洋で育て→再び湾内に」。船のドローン「マリンドローン」は既に販売をしている。それを使った密漁防止モデルの開発、※社会実装は「ものづくりスタートアップ・エコシステム構築事業」の補助を受けている。世界では炎だけという「生体群制御®」は魚の群れのコントロール。「微弱な電気を利用して魚の空間移動を促す」という。技術的にも法律的にも乗り越える壁はまだ高いそうだ。
※社会実装「科学技術の研究成果を社会問題解決のために応用、展開すること」
高校時代にスケート部を選択
中学生のときは卓球部。神奈川県横浜市の高校に進学し部活選びで考えた。「メジャーな競技ではなかなか大会に出るのは難しい。神奈川県ではマイナーで個人種目なら」。思い出したのは冬季長野五輪、スピードスケート500㍍で清水宏保が金メダルを取った。スケート部に入り、インター杯にも出場。大会があった盛岡市の県営スケート場は忘れられないリンクの一つだ。炎重工はこのリンクから約2キロ。「当時、会社があったのは滝沢村(現・滝沢市)。名前も聞いたことはなかった。それでも何かの縁があったのかもしれない」
技術好き、メカ好きの社長を支える
東京の自宅で“リモートワーク”をし、月に数回岩手県を訪れている。仕事は技術的なこと以外全部。営業、経理、総務、人事、企画、広報、そして一番多いのが雑務だ。社長が不得意なところは全部引き受け、社長には技術開発に専念してもらう。自分のキャリアと炎重工の将来図をしっかり描いている。現在35歳。40代までは「共感できる仕事をしたい」。50代までに「個人で稼ぐ力をつけたい」。会社は上場を目指し、世界にサービスを提供し「世界の飢えをなくす」。岩手県のものづくりベンチャーに転身して後悔はないのかという問いに「この5年間の経験は必ず将来に生きる」と自信を持って言い切った。

萩野谷 征裕(はぎのや・まさひろ):
東京都出身、1986年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、公認会計士資格を取得し監査法人に入社、上場企業の監査、ベンチャー企業のIPO(新規株式公開)支援に従事。ものづくり企業の監査を通して“ものづくり“の重要性を実感し、日本発の技術を使ったものづくりで食に貢献したいと2019年炎重工に参画した。
炎重工株式会社:
本社滝沢市。「制御技術」をコアにした自動化製品、サービス開発販売をしている。水産領域が得意で、魚などの群れ制御、水上ドローン、遠隔モニタリング用カメラなどを開発販売している。
\萩野谷さんの言葉を聞いた、参加者のコメント/
・とても面白いお話しでものづくりがこんなに進歩していると分かりびっくりです。ものづくりは面白そうと思いました。
・ロボットや機械を使い、食を守りたいという最先端の話を聞けて非常に興味深かったです。そんな技術を持った企業が滝沢市にあると知ることができて良かったです。ゲストの方の考え方や挑戦する姿勢はすごく素敵で自分も誇りを持って仕事ができる社会人になりたいと思いました。
・どんな考え方をして今の仕事につながったのか知ることができ参考になりました。自分が積み重ねてきたことのなかから、次の仕事を考えてみたいと思いました。
「しごとトークカフェ」は2010(平成22)年度にスタート。萩野谷さんは139人目のゲストでした。
