シゴトビトの言葉学
[第32講] 漆掻き職人 長島まどかのコトバ
毎月1回開催の「しごとトークカフェ」。そこで社会人のゲストが語る、働き方、暮らし方、生き方とは?岩手で働く社会人たちからのメッセージを「シゴトビトの言葉学」として紹介します。
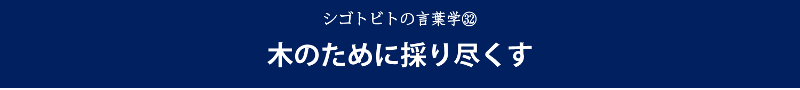 漆は、種や苗からなら約15年、立木伐採後の新芽なら約10年かけて成長した木から採る。6月ごろから始め半年をかけて漆を掻く。漆を出すことに慣れてもらうため、初めはゆっくり作業をする。1シーズンで1本の木から約200ccを採る。1人の職人が年間に扱うのは200~300本。雨の降り方や晴れの日がどのぐらい続いたか、葉の様子を観察して1本1本の“木の性格”に合わせカンナの深さを微妙に変える。それぞれの木に合った漆掻きをするのは「漆を採りつくすため」。漆掻きの季節が終わる12月、木にチェーンソーを当て、感謝を込め伐採する。再生のための儀式には「採り尽くす」ことが必要だ。
漆は、種や苗からなら約15年、立木伐採後の新芽なら約10年かけて成長した木から採る。6月ごろから始め半年をかけて漆を掻く。漆を出すことに慣れてもらうため、初めはゆっくり作業をする。1シーズンで1本の木から約200ccを採る。1人の職人が年間に扱うのは200~300本。雨の降り方や晴れの日がどのぐらい続いたか、葉の様子を観察して1本1本の“木の性格”に合わせカンナの深さを微妙に変える。それぞれの木に合った漆掻きをするのは「漆を採りつくすため」。漆掻きの季節が終わる12月、木にチェーンソーを当て、感謝を込め伐採する。再生のための儀式には「採り尽くす」ことが必要だ。
器用さを生かしたい
子どものころから手先は器用だった。高校を卒業し、フラワーアレンジメントやデザインを勉強するため専門学校に。在学中に「伝統工芸」「絵付け」「後継者」で検索して広島県熊野町の伝統工芸「熊野筆」の後継者育成事業の研修に3カ月参加した。卒業後、化粧筆の会社に就職。仕事は、毛先を完全にそろえ、半差しという小刀で逆毛やすれ毛を指先の感触を働かせながら抜き取る「逆毛とり」。指先の感触で行う微妙な作業も直ぐに覚え、7年間の経験で指導的な立場にまでなった。そんなときテレビで見たのは「所さん!大変ですよ」。国産漆の危機的状況を知った。熊野筆の仕事は発注者から求められる品質基準があり、それ以上技術を極める必要はなかった。その点、漆掻きは違うと、二戸市浄法寺町の地域おこし協力隊「うるしびと」に応募。第1期生として3年間の研修を終え、2019年4月、職人として独立した。
人と木とそして文化を育む
漆掻きは日の出から日暮れまで一日中、立ちっぱなしの仕事。当初は疲労がたまり、階段から転げ落ちたことも。研修生の中には漆かぶれで職人になることを断念する人もいる。修業を終え独立した今では免疫もつき、激しくかぶれることはなくなった。自分が掻いた漆は、国宝や重要文化財に指定されている日光東照宮の修復などに使われている。師匠からはほめられて育った。今は漆掻き職人として自活できているという喜びもある。しかし、職人としての技術レベルはまだまだ。1本の木から質の良い漆をいっぱい採りたい。そのために1本1本の木としっかり対話し、技術を磨き続ける。お手本になるような職人になり漆掻き職人を育て、ウルシの木を育て、そして漆器を日常で使う文化を育む。選んだ1字は「育」。それが夢でもあり目標でもある。

漆掻き職人:
岩手県は国産漆の約70%を生産している。毎年の生産量は1㌧前後で、二戸市浄法寺町は日本で一番、生産量が多い。同町の漆掻き職人は20数人で、同市は地域おこし協力隊員として後継者を募集している。
長島まどか(ながしま・まどか):
埼玉県上尾市出身。広島県で約7年間、熊野筆を製造する会社に勤務。二戸市の地域おこし協力隊「うるしびと」に応募。3年間修業し、2019年春に独立。
\長島さんの言葉を聞いた、参加者のコメント/
・手に職をつけるには、やはり根気強く、何年もコツコツと努力していく辛抱強さや、センスも関わってくるなと思った。
・手先の器用な職人に向いている人でも、生活費のために急いで漆を売らなければいけなくなるぐらい難しい仕事なんだなぁと思った。「やりたい!」という気持ちが生き方選びには重要だと思った。
・「こうあらねばならない」という固定観念を脱却した生き方で参考になった。
「しごとトークカフェ」は2010(平成22)年度にスタート。長島さんは127人目のゲストでした。
過去の様子はジョブカフェいわての施設内に常設のDVDで閲覧できます。
