シゴトビトの言葉学
[第26講] るんびにい美術館アートディレクター 板垣 崇志のコトバ
毎月1回開催の「しごとトークカフェ」。そこで社会人のゲストが語る、働き方、暮らし方、生き方とは?岩手で働く社会人たちからのメッセージを「シゴトビトの言葉学」として紹介します。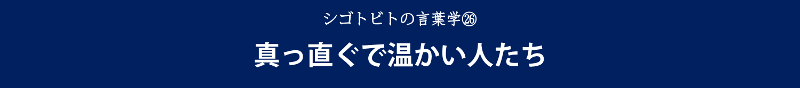
小さいころから人間関係に苦手意識があった。お調子者で目立ちたがり屋だったが、一方的なコミュニケーションで周囲から浮き上がることが多く、中学時代には「人なんかいなくなってほしい」と憂鬱さを抱えながら生きていた。それは成人してからも続き「就職して1日何時間も同僚らと過ごすのは無理。できれば仕事はしたくない」。絵を描くのが好きなそんな青年が地元の副住職から誘われ、寺が母体の知的障害者福祉施設に関わることに。障害に対するネガティブな先入観や差別意識もあったが、訪れた見知らぬ男に入所者たちは「こんにちは。何しにきたの」と声を掛けてきた。真っ直ぐで温かく、友だちにもなれる素敵な人たちだった。絵を描いている人や陶芸をする人もいた。小学校さえ行かず、美術など習ったこともないのに、緻密な美しい絵を描く障害者の存在に衝撃を受ける。
フリーターで美術家を目指す
人間関係が苦手だった高校生は、そのメカニズムを知りたいと心理学に興味を持ち、大学では神経心理学の研究をする。大学院も目指していたが、教授と対立して大学を飛び出し、実家に。しかし、就職する自信もなく「もう一度絵をやろう」と岩手大学教育学部の特設美術科に入学し銅版画を学んだ。卒業後、教員の道も頭にあったが、「働きたい」とも「働かないとだめ」とも思っておらず、「自称美術家というフリーター」暮らしに。カメラを手に自転車でぶらぶらと近所の風景を撮影して過ごしていたころ、お寺から声がかかった。福祉施設での仕事は週数回の非常勤で畑の作業の手伝いのほか、美術クラブの運営など。収入は安定せず、既婚で家族もいたため「子どもが小学生になるまでは美術家で頑張る」と期限を決め、借金をして個展などを開いていた。
テーマは「命ってなんだろう」
寺がつくった社会福祉法人光林会がるんびにい美術館の構想を打ち出したのが、ちょうど子どもが就学期を迎えたころ。これが最後と出展した公募展も落選し、るんびにいも含め美術・芸術関係の仕事はすべて辞めようと思っていた。しかし、光林会から「あなたがいるのを前提に美術館を立ち上げる」と頼りにされ、引き受けることに。結果として神経心理学の勉強や美術家としての活動などこれまでの経験が生かされる仕事に就くことに。
小さい挑戦を積み重ねて
「挑戦することを避け、逃げがあった」とこれまでの姿勢を反省する。自分のように自信がない人間にとって、なりたい何かがあり、その目標に達するためには小さいことでもいいので成功体験を重ねることが必要という。やるかやらないかの選択肢に出会った時、それがささいな問題である時こそ「今回はパス」と思うのではなく「少しでも役立つならやってみよう」と小さな挑戦のサイクルを積み上げる。「不確実なことには挑まないというのではなく、シンプルにただチャレンジすることが目標に近づく唯一の道」
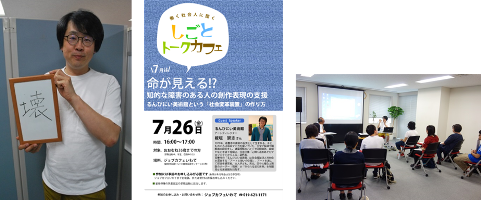
るんびにい美術館:
花巻市星ケ丘1丁目。社会福祉法人光林会が運営する「アートと憩いの空間」で、アートを通して障害者健常者、大人子ども、男女、国や人種など、この世にある無数のボーダー(境界)が「作られる前の世界」を垣間見せる美術館を目指す。
板垣 崇志(いたがき・たかし):
1971年、花巻市石鳥谷町の農家の長男として生まれる。子どものころは毎日マンガを描いていた。大学で脳波や銅版画の研究をし、建築現場のバイトや印刷会社、絵描きなどを経て現職に。任意団体「心輝く造形あそびプロジェクトからふる」副代表。
\板垣さんの言葉を聞いた、参加者のコメント/
・現在は全く関係ない仕事に就いているのですが、最近福祉分野に興味があり、今回お聞きした考え方を、仕事を選択する上で参考にしていきたいと思います。
・福祉の職に就くにあたり、どういう意気込みで臨むのが良いのかを改めて考えさせられました。障がいがあったとしても、特別扱いをすることなく、1人の人間として捉えて関わりを深めていくことが大切になるということを実感しました。
・常に“悩める人”なんだなというのが伝わった。人間って悩む生きものだと思うんですけれど、その意味で人間らしい歩みだなって思って聞いていました。
「しごとトークカフェ」は2010(平成22)年度にスタート。板垣さんは121人目のゲストでした。
過去の様子はジョブカフェいわての施設内に常設のDVDで閲覧できます。
