シゴトビトの言葉学
[第11講] 企業組合八幡平地熱活用プロジェクト代表理事 船橋慶延のコトバ
毎月1回開催の「しごとトークカフェ」。そこで社会人のゲストが語る、働き方、暮らし方、生き方とは?岩手で働く社会人たちからのメッセージを「シゴトビトの言葉学」として紹介します。
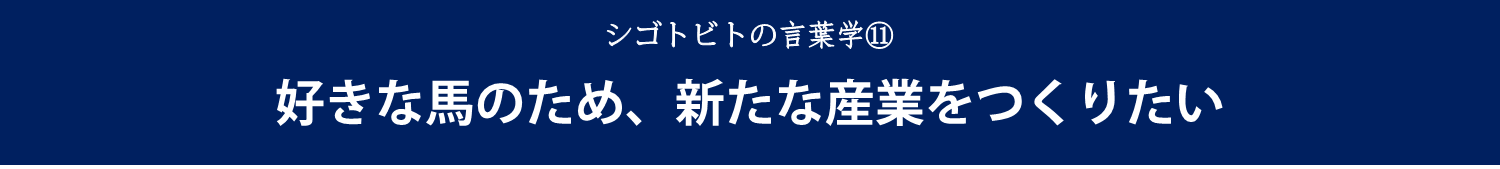 大阪のお好み焼き屋に生まれた船橋は、小さいころは子ども歌舞伎に熱中し、けいこに明け暮れる。中学生になると「風のシルフィード」など競馬漫画を愛読。週末開催の競馬の勝ち馬とレースの様子をすべてそらんじられるほどに。目指す仕事は「騎手か厩務員」。このころから馬中心の人生を送ることになる。なかなか凡人にはできないことの一つが「好きなことを続ける」。馬術競技で東京五輪を目指す船橋は、少年の心を持ち続ける若者だった。
大阪のお好み焼き屋に生まれた船橋は、小さいころは子ども歌舞伎に熱中し、けいこに明け暮れる。中学生になると「風のシルフィード」など競馬漫画を愛読。週末開催の競馬の勝ち馬とレースの様子をすべてそらんじられるほどに。目指す仕事は「騎手か厩務員」。このころから馬中心の人生を送ることになる。なかなか凡人にはできないことの一つが「好きなことを続ける」。馬術競技で東京五輪を目指す船橋は、少年の心を持ち続ける若者だった。
東日本大震災を機に
岩手県に移住する前、北海道の競馬馬育成牧場で働いていた。理学療法士の妻は乗馬クラブでホースセラピーを担当。子ども二人を保育園に預け、夫婦で朝から晩まで仕事をする日々だった。そんなとき東日本大震災が発生、「このまま今の暮らしを続けていいのか」と妻と話し合い、以前訪れたことがある八幡平市のクラリー牧場に移ることに。牧場は経営難で、当初は余剰の馬を処分することが仕事だった。
馬ふんと地熱とマッシュルーム
そんな中、クラリー牧場が生産していた馬ふん堆肥が「農業に最適」と軽トラックで買っていく方がいた。「これは商売になるのでは」。馬ふんが堆肥になる過程では、一定の温度があって発酵がうまく進む。しかし、冬が寒い八幡平市では好気性細菌に酸素を与えるため撹拌すると堆肥温度が急激に下がってしまう。そこで目をつけたのが、地熱だった。企業組合八幡平地熱活用プロジェクトは、資源エネルギー庁の地熱理解促進関連事業から1億7千万円の補助を受け、2014年9月に設立。地熱を使った馬ふん堆肥で月に5トンのマッシュルームを生産し、いわて生協などに販売している。
「堆肥馬」という新たな産業を
「国内には競馬、乗馬、馬肉の三つの産業しかない。これに『堆肥馬』という新たな産業を加えたい」。馬は現在16頭いる。企業組合とは別会社にし、船橋夫妻と70代の男性が世話をして堆肥をジオファームに販売している。マッシュルームが軌道に乗ったというものの、生産量や販売価格をもっと上げないと、厩舎の維持もままならない。「馬ふん堆肥の販売で厩舎を運営し、岩手山麓を馬が駈け巡る風景や環境を守るのが自分の夢」。大阪生まれの若者が岩手の馬事文化を担っている。

企業組合八幡平地熱活用プロジェクト:
2014年設立。馬ふんを使った堆肥(たいひ)と地熱を利用し、マッシュルームや季節によっていろいろな野菜を生産、販売している。組合メンバーは代表理事の船橋慶延さんを入れ7人。ほかにパート従業員がいて、現場では毎日14、15人が働いている。
船橋 慶延(ふなはし・よしのぶ)氏プロフィール:
大阪市出身。1982年生まれ。高校で乗馬と出会い、学生時代馬術(障害飛越)に熱中し、卒業後は北海道などで競走馬の育成に携わる。「引退した馬がゆっくり余生を過ごせる場所をつくりたい」と2012年に岩手県八幡平市に。障害飛越など馬術競技を続け、2020年の東京五輪出場を目指している。
\船橋さんの言葉を聞いた、参加者のコメント/
・今まで知らなかった世界の話を聞くことができ、参加して良かった。自分の仕事観を再考したい。
・関心のない分野でしたが、岩手の良さやクリーンエネルギー、馬文化継承の可能性を学ぶきっかけになった。
・好きなことを仕事にすることが、仕事に対する熱意にもつながっているのだと感じた。新しいことへの挑戦を常にしているのが発展にもつながっているように見えた。
「しごとトークカフェ」は2010(平成22)年度にスタート。船橋さんは104人目のゲストでした。
過去の様子はジョブカフェいわての施設内に常設のDVDで閲覧できます。
