シゴトビトの言葉学
[第10講] 岩手くずまきワイン 製造部製造課生産管理担当 小野寺望のコトバ
毎月1回開催の「しごとトークカフェ」。そこで社会人のゲストが語る、働き方、暮らし方、生き方とは?岩手で働く社会人たちからのメッセージを「シゴトビトの言葉学」として紹介します。
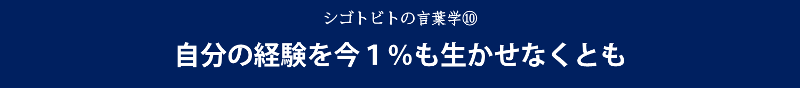 小野寺は生命科学の実験研究が楽しくて大学院に。「もっと結果を出したい」と博士課程にも進み、長年の研究を学術博士号取得という形で結果にした。ここからの進路は限られる。大学に残り教授を目指すか、大企業の研究所などで研究職に就くか。しかし、被災地大船渡市出身の小野寺は「岩手のために貢献したい」と葛巻町のワイナリーを選ぶ。
小野寺は生命科学の実験研究が楽しくて大学院に。「もっと結果を出したい」と博士課程にも進み、長年の研究を学術博士号取得という形で結果にした。ここからの進路は限られる。大学に残り教授を目指すか、大企業の研究所などで研究職に就くか。しかし、被災地大船渡市出身の小野寺は「岩手のために貢献したい」と葛巻町のワイナリーを選ぶ。
研究室にこもる日々
幼稚園から高校まで大船渡で暮らし岩手大工学部に。当時は福祉システム工学科があり、医療福祉関連の仕事をしたいという漠然とした思いと「介護ロボットなんかも面白そう」という軽い気持ちだった。実際に選んだ研究テーマは、視覚情報を処理する脳は発生過程でどんな遺伝子が機能しているのか。「研究は楽しかった」。ニワトリの受精卵やマウス、線虫などを扱い、研究室にこもる日々を過ごす。
過去にこだわらず新しいことに挑戦
大学4年生のころは研究中心の生活になり、同時に進学か就職か悩む日が続く。やがて「もっと結果を出したい」と思うようになり進学を決意。しかし研究に打ち込んでいた修士課程1年のとき、東日本大震災が起きる。自宅は高台にあり被災しなかったものの、母親が津波に巻き込まれ亡くなり、ふるさとは壊滅的な被害を受けた。「岩手に貢献したい」そんな気持ちを抱きながら研究を続け、博士課程を終える。新たな進路の決断を迫られ思ったことは「新しいことを取り入れるためにはこれまでの分野にこだわらない」。博士号を持ちながら新卒としての就活も始めた。
できることを増やし自分を生かす
工業製品の製造やプラント関連職種、医療関連の営業などの受験にも挑戦。しかし、直接言われることは少なかったものの「どうして博士号のあなたがわが社を」と高学歴が就職のネックになった。そんななか、比較的反応が良かったのが食品会社だった。食品関係の会社を岩手県内で探しているうちに葛巻ワイナリーに出会った。大船渡で仕事をすることが直接の地元貢献。でも岩手で働くことも貢献の一つ。「自分が学んできたことと仕事には正直ギャップを感じることもあるが、自分にしかできないことをこれから増やしていきたい。将来は葛巻町内に『山ぶどうの研究所』をつくりたい」

株式会社岩手くずまきワイン:
1986(昭和61)年設立。本県が生産量日本一の山ぶどうを葛巻町が特産品化しようと、ワイナリーを開設。製品は国内ワインコンクールなどで各賞を獲得している。旧社名は「葛巻高原食品加工株式会社」
小野寺 望(おのでら・のぞみ)氏プロフィール:
大船渡市出身。大船渡高校卒業後、岩手大学工学部へ。生物工学などを学び、大学院で学術博士を取得。2016(平成28)年4月に(株)岩手くずまきワインに入社し、製造部製造課で生産管理などを担当している。
\小野寺さんの言葉を聞いた、参加者のコメント/
・高学歴でも一般の方々と対等に働いていることを聞くことができてとてもよかった。新しいことにチャレンジするきっかけのヒントみたいなものを見つけられた気がする。
・ワイン造りを含めた仕事の話だけではなく、就職活動についての話も印象に残りました。「固執しすぎない」「学んだことが(人に認められて初めて)後からついてくるようにすればいい」など響く言葉がありました。
・こんな生き方もあるんだなぁと考えるきっかけになりました。自分に近い部分があるとも思いました。
「しごとトークカフェ」は2010(平成22)年度にスタート。小野寺さんは103人目のゲストでした。
過去の様子はジョブカフェいわての施設内に常設のDVDで閲覧できます。
